ここ数年、「BCP(事業継続計画)」の策定が国レベルでも強く推奨されるようになっています。特に医療・介護業界では、義務化の流れも進んでいます。
では、なぜ国がそこまで言うのか?
その理由は、以下のような背景があります。
1. 災害大国・日本の現実
日本は地震、台風、水害、火山噴火など自然災害のリスクが極めて高い国。
大災害のたびに、医療・介護・福祉の現場が深刻な混乱に陥ってきました。
→ そのたびに「備えが足りなかった」という反省が繰り返されてきたのです。
2. 高齢化社会で、止められないサービスが増えている
特に介護やリハビリといった人の手で支えるサービスは、
災害時でも止めてしまえば「命」に関わります。
→ 国としては、「非常時でも継続できる体制づくり」が急務。
 | 世界1位 ビール & 金賞 ハム・ソーセージ 詰め合わせ ベアレン 定番ビール セット 冷蔵便 【クラフトビール お中元 ビールギフト 飲み比べ 本格 誕生日 おつまみ ギフト 肉 内祝い お酒】 価格:4100円~ |
3. 感染症の教訓(コロナ禍)
2020年以降のコロナウイルス感染拡大で、
人手不足 医療崩壊 施設内クラスター 物資不足
といった「有事に動けない」現実が露呈しました。
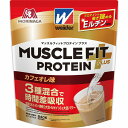 | 価格:5702円 |
→ この経験を機に、国は「BCPの策定」を制度として強く推進し始めたのです。
4. 制度としての義務化の流れ
介護・医療分野では、以下のようにBCPの策定が制度化されています。
2021年介護報酬改定 → 介護事業所に対し、感染症と災害の両面に対応したBCPの策定が義務化(猶予あり) 障害福祉サービスも対象 → 同様にBCP策定が求められており、今後さらに対象が広がる見込み
5. 国の基本方針(内閣府・厚労省)
内閣府の「防災基本計画」、厚労省の「業務継続計画ガイドライン」などでも、
各施設が自助・共助の視点で備えること 有事でも「地域の医療・介護機能を維持する」こと
が明記されています。
まとめ:BCPは国全体の「生命線」
国がBCPを求めるのは、
「一つの施設・病院の問題」ではなく、
社会全体の安全保障につながるから。
そして、リハ職や介護職など現場の人間がBCPに関わることで、
より実効性のある、使える計画にすることができます。
 | お買い物マラソン!加温式折りたたみフットバス TKSM-026(※沖縄及び離島へのお届け不可) 価格:9493円 |


